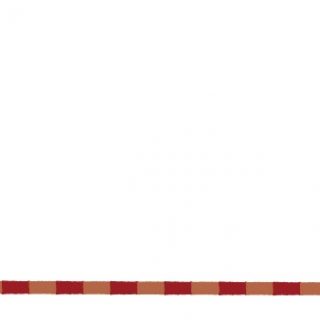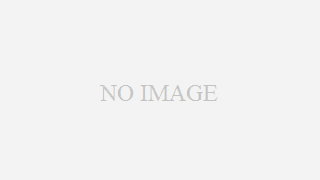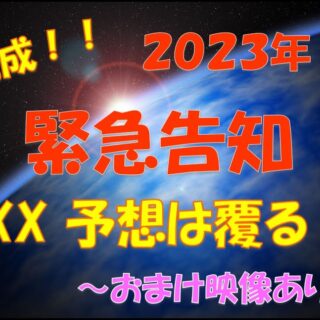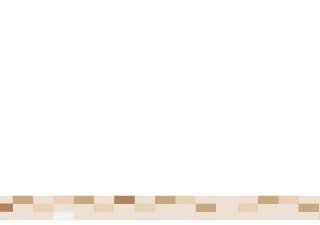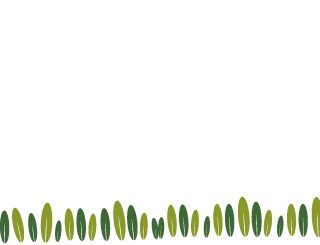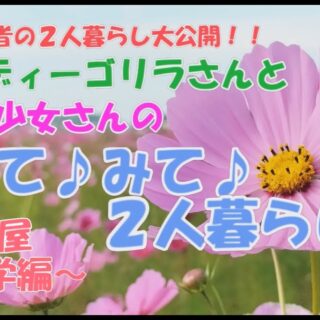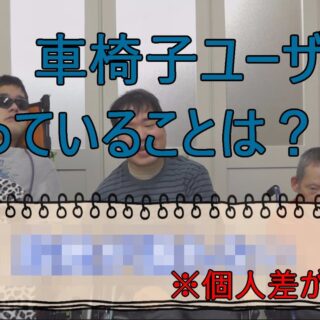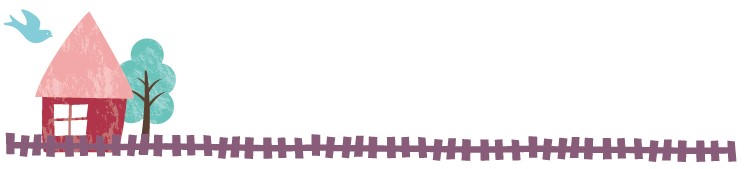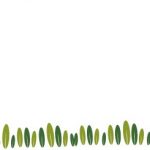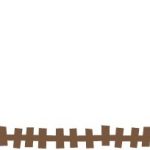在宅介護の支援のポイント
今回は、実際にサービス利用者やヘルパーさんから言われた話を私なりに、在宅介護の特徴や支援する際のポイントとしてをまとめてみました。
在宅支援のポイント
・利用者の価値観を理解する。
・体力的負担の軽減を考える。
・使用した物は、元の位置戻す。
・利用者には生活空間、介助者には職場である事を理解する。
・利用者と1対1になる。
・出来ない事は丁寧に断る。
・家庭内の事を必要以上に覗き見たり、聞いたりしない。
・調味料や日用品が切れたり、新しい物を開ける時は声をかけましょう。
他にもたくさんあると思いますが下記でそれぞれ解説しています。
利用者の私物を使用する機会が多い。
施設などと異なり、基本的には利用者の私物を利用することが多いです。その際にきをつけてもらいたいのが、例えばティッシュ1枚も利用者の私物、トイレを借りる際も私物の利用と言う事を頭に入れておきましょう。ティッシュやトイレを利用は、利用者は慣れてはいますが、一言声をかける事が大切だと認識すると利用者との良い関係が築きやすいと思います。過去に勝手にエアコンやTVをつけるヘルパーさんがいて不快に思われる利用者がおられました。
利用者の価値観を理解する。
例えば、食材の賞味期限が切れていた場合どうしますか?人により物により判断が異なると思います。自分の価値観で判断せずに利用者に確認していくことが大切です。他にも自分は安いと感じるものが利用者には高いと感じたり、もちろん情報提供は必要ですが利用者の価値観に合わせることが大切です。ヘルパーさんの価値観を押し付けると利用者の関係性が悪くなることがあります。
体力的負担の軽減を考える。
施設や病院と異なり、在宅では介護リフトやベット、介護スペースの確保、段差の解消ができないケースも多くあります。それゆえに体力的に負担が多くなりやすいケースもあります。その場合は、サービス提供責任者に相談すると良いと思います。適切な介助方法を学ぶ事でに体力的な負担を減らす事が可能になるかもしれませんし、適切な介護用品の導入や環境設定をすることで体力的な負担を減らす事ができます。また、適切な介護方法を学ぶ事も解決の方法に繋がるかもしれません。
使用した物は、元の位置へ戻す。
利用者によっては、物の位置を全て覚えてヘルパーに指示する方もいます。場所が少し変わるだけでその指示が伝わらなかったりして不便になります。そうならないように使用した物や片づける場所には、気を付けましょう。利用者に確認できる場合は、不安があれば確認して元の位置に戻すようにしましましょう。思い込みや適当な場所になおさないように注意しましょう。
利用者には生活空間、介助者には職場である事を理解する。
多くのヘルパーさんは、在宅は利用者の生活空間である事は理解してくれていると思います。たまに理解していなく、まるで自分の自宅かのようにされるヘルパーさんもおられるのでそうならないように注意しましょう。
また、介助者にとっては職場である事も理解しましょう。利用者の生活空間を職場にしています。ここでお伝えしたいことは、良い仕事をするためには、職場環境も大切と言う事です。
例えば、キッチンが別室で調理を頼まれました。真夏は当然暑くエアコンをつけたいと利用者に頼みましたが電気代が…と言われて拒否されました。当然、ヘルパーさんは暑くて過重な仕事をすることになりました。これでは良い職場環境とは言えません。そういった場合は、サービス提供責任者に相談することをお勧めします。もちろん我慢することが悪い事ではありませんがいい仕事をするためには最低限の職場環境が必要だと思います。当法人のヘルパーさんで過去にかなり我慢してヘルパー活動していた事があり、辞めたいとの話にまでなってやっと発覚したケースがあります。
利用者と1対1になる。
当然ですがヘルパーさんは多くの場合、利用者と二人で1対1になる事が多いです。そこで気を付けてもらいたいのが、「無言の時間」です。「無言の時間」はなんとなく気まずさや愛想がないとおもわれるのではないか?や利用者の事を思うといっぱい話しかけて楽しい時間を過ごしてもらおうと考えてくれるヘルパーが多くいます。では、仮に起きてから寝るまでヘルパーさんが交代で入っている利用者だとしたらどうでしょうか?ヘルパーさんにとっては自分の入っている3時間を楽しい時間にしたいと思いいっぱい話をします。すごく良い心がけだと思います。ただ理解してあげて欲しい事は、ヘルパーさんにとっては、3時間ですが利用者にとっては5人のヘルパーさんで計15時間になるという事です。私が利用者なら15時間ずっとお話されていたら流石に疲れてしまいます。もちろん初めのうちは難しいと思いますが慣れてくればゆったり過ごせる「無言の時間」も大切にしてくれるヘルパーさんも私は素敵だと考えて支援しています。利用者によってはお話好きな方や静かだと嫌な方もおられますし、少ないヘルパーの時間の場合はいっぱいお話することは喜ばれるかもしれません。利用者の様子や生活環境を見ながら判断してもらえれば良いと思います。また、たくさん話過ぎるるヘルパーも良いとは言えないので「利用者の話を聞く」ことを大切にすると良いでしょう。
出来ない事は丁寧に断る。
ヘルパーさんは、出来る支援とできない支援があります。制度のルール上できない支援や、事業所の方針、またはヘルパーの苦手な事、出来ない事を頼まれる事もあります。その場合は、丁寧に断る事が大切です。「他のヘルパーさんはしてくれるのに…」などと言われる事もあります。その場合は、サービス提供責任者に相談することが良いと思いもいます。「これくらいならOKか…」と勝手に判断する事は危険です。また我慢しすぎてストレスをためと良い支援はできません。
家庭内の事を必要以上に覗き見たり、聞いたりしない。
支援に入るといろいろな物を見たり、聞いてしまう事があります。同居している他の家族の生活スペースが見えてしまう事もありますし、利用者のプライベートな話まで聞きすぎてしまい不快に思う利用者もいます。もちろん良い支援や良いコミュニケーションをするために情報収集は必要です。目的をきちんと持って情報収集しましょう。またサービス中に得た情報は利用者の個人情報になりますので、個人情報取り扱いにはくれぐれもきをつけましょう。個人情報の取扱いについては「福祉サービス利用者の個人情報について」で詳しく解説しています。
※「虐待かな?」と感じる現場を見り聞いたりした場合は、支援者には通報の義務があります。虐待と判断するのは支援者の仕事ではありません。
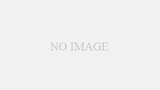
調味料や日用品が切れたり、新しい物を開ける時は声をかけましょう。
調理をヘルパーさんにお願いされることはよくあります。その際、当然調味料や食材などを使いますが食材などを使用した量は出来るだけ伝えていきましょう。調味料は、細かく伝える事は少ないと思うので少なくなってきた際やなくなった際には伝えるようにしましょう。日用品も同様です。新しい物を開けた際は、予備の残数も伝えるとより良いと思います。
まとめ?
この記事をまとめていて、今までいろんな話を聞いたなと思いだしました。今回は、簡単にまとめてしまいましたが話を聞いた利用者やヘルパーさん達は皆さん切実に悩んでおられたなと思いました。そんなヘルパーさんや利用者の力になれればと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
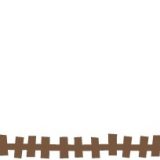
も読んで頂けると嬉しいです!!